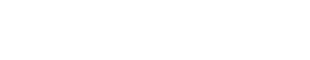史上最強の哲学入門
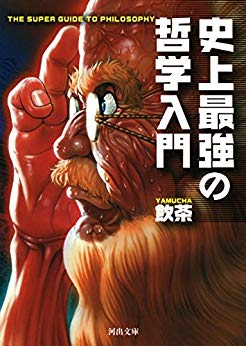
こちらで購入可能
圧倒的な分かりやすさ!
哲学入門の参考文献筆頭が「グラップラー刃牙」って、
要約
真理の「真理」
- プロタゴラス
「人間が万物の尺度である」として、絶対的な真理などはなく、価値観は人それぞれだ、という相対主義を説く。
かつてはそれぞれの社会で神話が素朴に信じられてきたが、地域を超えた交流が広がるにつれ神話の内容が複数あり、どれかが絶対的に正しいとは言えないことが分かってくる。
民主主義体制だった古代ギリシアで論争に勝つには、相対主義で話のポイントをずらす技術が重宝された。
- ソクラテス
相対主義により「絶対的な真理」を求める気持ちが失われていく。古代ギリシアでも何ごとも絶対的に決められないから適当でいい、という雰囲気からクチの上手い政治家が権力を持つ「衆愚政治」に陥っていた。
ソクラテスは相対主義を是とせず、絶対的な真理を求めるべきだと考え、政治家たちが「本当に正しいこと、本当の善」を理解していないということを論破した。ソクラテス自身も真理を理解しているわけではなく、自分が無知であることを自覚し(無知の知)、「だから一緒に考えよう」というスタンスだった。「何も知らない」という自覚があるからこそ「真理を知りたい!」という気持ちが生まれてくる。
- デカルト
キリスト教が西洋を支配する中世には「人間は理性だけで審理に達することはできず、紙への信仰が必要」という方向に進んだ。
その後、ルネサンスや宗教改革を経て教会の権威が弱まり、人間の理性を再評価する近代に突中する。
数学者でもあったデカルトは、数学が絶対的な公理をベースに定理を重ね論理体系を作るのと同じように、真理を追究していくのにも、まずは確実な「第一原理」を見付けようとした。
全てのものを疑ったとしても「疑っている主体がいる」ことは否定できず「我思う、ゆえに我あり」として絶対的な真理のベースとした。
- ヒューム
デカルトが「私の存在は確実だ」としたところから「不完全な私が完全な神を認識できるのは神が存在するからだ」「神が作った私の認識は明晰だ」と理論を重ねた。
これに対しヒュームは経験論の立場から「『私』というのは近くの集まりに過ぎない」とし、また「人間が神をイメージできるのは複数の観念を組み合わせているからだ」とした。
- カント
ヒュームの言うように、全ての観念は人間が経験から作り出したのだとすると、多くの人間同士が通じ合えるのは何故かと考えた。
そして人間には経験の受け取り方に「時間的・空間的な情報として理解する特有の形式」があり、それは経験に拠らない「先天的」なものだと考えた。だから「人間の間では」普遍的な真理を見付けることは可能だとした。
- ヘーゲル
カントは「人間にとっての真理」があることを説いたが、そこに辿り着く方法は説明しなかった。
ヘーゲルは弁証法をとなえ「対立する考えをぶつけ、その両方を解決する上位の真理を見つける」ことを説いた。歴史は闘争の果てによりよい社会になっていくと考えた。
- キルケゴール
ヘーゲルの弁証法によれば、いつか誰かが究極の真理を見付けるかもしれない。
だがキルケゴールは、人類にとっての普遍的な真理より「『私』にとって真理だと思える真理を見付けることが需要なのだ」とした。
- サルトル
ヘーゲルとキルケゴールの対立を受け、サルトルは「いっそ自分たちの手で歴史を進めることに人生をかけてみよう!」と提言し、当時の若い世代を動かした。
- レヴィ-ストロース
レヴィ-ストロースはサルトルに対し「人類が目指すべき歴史」など本当にあるのか、という疑問を投げかけた。
人類学者であったレヴィ-ストロースは西洋人が「未開」だと考えていたアマゾンなどの社会に、西洋とは異なる合理的で深遠な社会システムがあることを発見し、「西洋の歴史の進展が唯一の正解」だという傲慢さを否定した。
- デューイ
二度の世界大戦を通じ、人間の理性を信頼した近代哲学の楽観的な主張は力を失った。「理性によって心理に到達しよう」という近代哲学への批判から生まれた現代哲学の一つとして「真理かどうかより役に立つかどうか」を考えるプラグマティズムが生まれる。
デューイは「道具主義」を提唱し、人間の理性は生きるための道具だと考えた。例えば「人を殺していなないのは何故か」という問題は「人を殺したら悪い、という決め事は何の役に立つのか」と考えるべきだとした。
- デリダ
ポスト構造主義の旗手であるデリダは、西洋文明が音声中心主義(話し手中心主義)であると批判した。
話し手が意図した「正解」を、読み手が正確に受け取ることが大事とする「話し手中心主義」に対して、受け取り側(読み手)のそれぞれの解釈が正解でいい、とした。相手に正確に意図が伝わったかどうかも最終的には言葉で確認するしかなく、言語での伝達が完全であることの照明は原理的にできない。
現代では真理を追究するのに弁証法の考えで衝突を繰り返せば、全人類を滅ぼす戦争に発展しかねない。衝突を避けるためには相対主義で考えざるを得ない。
また、哲学以外の分野でも物理学での不確定性原理の発見や、数学での不完全性定理の発見など「到達しえない範囲」があることが明確になった。
- レヴィナス
自分がいなくても変わりなく動いていく世界や、原理的に理解不可能な事柄など「他者」があり、どれだけ世界を完全に記述しようとしても、その外側の「他者」が生まれてしまう。
「他者」は真理への到達を妨げる存在ではあるが、「他者」があるからこそ無限に問いかけ続けることができるとも考えた。
国家の「真理」
- プラトン
プラトンはソクラテスを死に追いやった衆愚政治を憎み「イデア=究極の理想」を理解した優れた人間が哲人王になり統治すべきだとした。
- アリストテレス
アリストテレスはプラトンの教え子であったが「イデアは本当にあるのか、あったとして何の役に立つのか」という疑問を投げかけた。
アリストテレスは、君主制は独裁に陥りやすく、貴族制は権力闘争に陥りやすく、民主制は衆愚政治に陥りやすいとし、どのような政治体制であっても最良に保つ努力をしなければ腐敗し、別の政治体制に移行すると考えた。
- ホッブズ
ホッブズは「人間は本来利己的で放置すると争い始めるので、互いに共存するため架空の支配者として、国家という仕組みを作り上げた」とする社会契約説を唱えた。
- ルソー
ルソーは「人間は本来的にはお互いに助け合って生きるものだ」とし、自然状態で闘争が起こるとしたホッブズの考えを否定した。その上で国家は民衆にとって必須なものではなく、 人民に幸福をもたらさない国家は解体してもっと良い国家に作り変えればいい」と人民主権を訴え、後のフランス革命にも影響を与えた。
- アダム・スミス
市民革命により政治体制が民主主義へと移り変わり、次に課題となったのが経済の問題だった。
キリスト教圏では個人が富を蓄えることは卑しいと考えられていたが、アダム・スミスは「それぞれがお金儲けに走れば、全体として上手くいく」と唱えた。それぞれが利己的に動いても「見えざる手」が適切な落とし所に落とす、という考え方。
- マルクス
アダム・スミスの提唱した利己的な経済社会=資本主義社会は成功をおさめたが、マルクスは「資本主義は人を不幸にするシステムで必ず破綻する」と言った。
資本家は労働者の生み出した富を搾取するだけでなく、資本家同士の競争のしわ寄せが労働者に行く仕組みを解き明かした。そして資本主義のあとの理想的な経済体制として共産主義を提唱した。
神様の「真理」
- エピクロス
アレクサンドロス大王の侵略で故国を失った人々を支えようとする哲学が生まれた。「世間的な幸せを放棄するキュニコス派」「禁欲的に生きるストア派」「気持ちいいことをすればいいとするエピクロス派」の3つが主なもの。
エピクロスは「全知全能の神がいたとしたら、人間のことなど気にかけない。人間は神のことなど気にかけなくていい」とした。
- イエス・キリスト
苦難の歴史を経てきたユダヤ教徒は、敵国を排除するような強い救世主を求めていたが、イエスは「愛」を説いた。ユダヤ人を特別扱いすることもなく、ユダヤの救世主を望む人々の怒りを買い、捕らえられた処刑されてしまう。
イエスの復活を信じた弟子たちがキリスト教を広める活動を始めた。
- アウグスティヌス
ローマ帝国でキリスト教が公認されてから内部分裂が起こったが、アウグスティヌスが教義をまとめ上げた。
「完璧な絶対神がなぜ悪を許すのか」という疑問には「闇が光の不在であるのと同じく、悪は善の不在である」とし「神が人間を愛するゆえに自由意志を与えたので、神の意図から外れる行動をとるという原罪を背負っている」と答えた。
またアウグスティヌスは、自分自身にも欲望に負けてしまう弱さがあることを認め、それゆえ神への懺悔が必要だとした。
- トマス・アクィナス
12世紀ごろ、アリストテレスの著作がラテン語に翻訳され、キリスト教圏に伝わってきた。アリストテレスの理路整然とした論理学がキリスト教の教義と矛盾してしまう。
トマス・アクィナスは理論を突き詰めても「最初の原因」を知ることはできないとし、「原因と結果という関係を超越した何か」を想定する必要があるとして哲学の領域と神学の領域は扱うレベルが違うとした。
- ニーチェ
ニーチェは「神とは弱者のルサンチマンが作り出したものに過ぎない」とし、人間本来の「強いことは素晴らしい」という価値観を殺しているとした。
「現実の復讐を望むユダヤ教」から「無抵抗、自己犠牲を善とするキリスト教」に移行した時に「弱いことが善」という価値観が広がった。しかし本来人は「金と権力」を欲するのが自然で、手に入れられないからその価値を貶める。それは「すっぱいぶどう」的なルサンチマンだと批判した。
人が神を殺してしまった現代で「強くなりたいという意志をしっかりと自覚し、そこから目を背けない 超人」として生きることを提唱した。
存在の「心理」
- ヘラクレイトス
ヘラクレイトスは「万物は流れ去る」とし「この世に不変の存在はなく、形あるののはいつか壊れて、その形を変えて流れ去っていく」と考えた。
石は砕けて砂になり大地の一部となり、やがて大地から木が生え、りんごが育つ。石は姿を変えリンゴになっていると言える。そうした変化には万物共通の法則があると考え、その法則をロゴスと呼んだ。
- パルメニデス
パルメニデスは「存在とは決して変化しない『何か』だ」と述べ「存在している『有』は決して『無』にはならない」と考えた。
例えばリンゴをどれだけ小さく刻んでも小さくなるだけで消えて無くなることはないとした。
- デモクリトス
ヘラクレイトスの「万物は流転する」という考えと、パルメニデスの「存在は変化しない」という考えを矛盾せずに統合したのが、デモクリトスの原子論。
それ以上分割できない「原子」は決して変化しないが、その原子が一手の規則に従って結合したり分離したりすることで、万物が変化するように見えているとした。
- ニュートン
ニュートンは万有引力の法則で、地上のリンゴが落ちる力と、星が巡る力が同じものであることを説明し、天体は特別なものという認識を変えた。
- バークリー
バークリーは「存在とは知覚されることである」とし、リンゴの存在は物質があることでなく知覚することから始まるとした。少なくても物質が「ある」ことを知覚を通さずに証明することはできない。
- フッサール
自分が知覚している世界の現象は「別世界の水槽に浮いているのうが見ている夢」である可能性を否定することはできない。
そう考えるとニュートンの力学体系もデモクリトスの原子論も真偽不明の思い込みに過ぎないという可能性もある。
全ての確信は「主観的な意識体験」から生まれているとし、それが夢であろうと「こういう主観的な意識体験があるから、こういう世界観や科学理論を持つに至った」ということはできると考えた。
- ハイデガー
フッサールのでしハイデガーは「存在とは人間の中で生じるもの」だと考えた。「存在とは何か」という問いは「人間にとって存在するとはどういうことか」という問いに還元されると考える。
ハイデガーの著書「存在と時間」は未完で彼の論旨は不明のまま。
- ソシュール
言語学者のソシュールは「言語とは差異のシステムである」と考えた。区別する価値があるから言葉が生まれるのであり、言語体系の違いは区別体系の違いだと言える。
リンゴを皿や周辺の空気と区別することに価値があると考えるから、リンゴという言葉が生まれる。例えば有機物を食べない超巨大な宇宙人にとってリンゴは無価値な小さな点であり言葉で区別することがないなら、リンゴは存在しないことになる。
感想・考察
飲茶さんの「分かりやすく・面白く」解説する技術は圧倒的だと思う。
哲学というと小難しくて敬遠されがちだ。だが「厳密に語るため複雑になっている言い回し」を排除して、エッセンスを取り出すと、常識と思っていたことが壊されたり、まったく新しい見方が発見できたり、脳が揺さぶられるような刺激がある。
まずは哲学の面白さを感じるための入門書として最適な一冊だと思った。