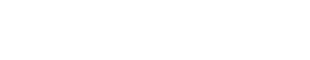私が大好きな小説家を殺すまで

こちらで購入可能
あらすじ
小学生の幕居梓は母親に虐待されていた。
梓が学校から帰ってくると、母親が連れ込む男に見られないように押入れに閉じ込められていた。梓は大好きな本を諳んじ、押入れの中の孤独に耐えていた。中でも遥川悠真の小説をこよなく愛し、救いを感じていた。
ある日、遥川の新刊を図書室で借りて帰ったことが母親に見つかる。本は破り捨てられ、書店で同じ本の万引きを強要された。
そして翌日には母親はわずかな金を置いて家を出ていった。
母親に見捨てられた梓は自殺を考える。
大好きな遥川の本を手に踏切に飛び込むタイミングをはかっていると、ひとりの男が「迷惑なんだよね」と声をかけてきた。彼は遥川本人で「自分の小説を持って自殺されると悪評がたつから止めてくれ」という。
梓の事情を察した遥川は、彼女を自宅に連れて帰った。
それから小学生の梓と遥川の共同生活が始まった。
梓は、憧れていた作家が目の前で創作に取り組む姿に感動し、それまで以上に深い敬愛の念を持つようになる。
だが、最新作が酷評され、遥川はスランプに陥り全く書くことができなくなる。
やがて中学生になった梓は、遥川へのラブレターとして自分の書いた小説を贈った。遥川の文体や雰囲気を完璧に模した作品は、彼の小説の素晴らしさを讃えるものだった。
だが二人の関係はそこで大きく捻じれてしまった。
才能の枯渇を感じていた遥川は梓の書いた小説に打ちのめされる。
そして彼女の小説を自分の作品として発表してしまった。
梓は遥川のゴーストライターとして、小説を書き続けていく。
感想
二人のすれ違いが悲しいバッドエンドだ。
梓の独白はこんなフレーズから始まっている。
『憧れの相手が見る影もなく落ちぶれてしまったのを見て「頼むから死んでくれ」と思うのが敬愛で「それでも生きてくれ」と願うのが執着だと思っていた。だから私は遥川悠真に死んで欲しかった』
梓にとって遥川と彼の書いた小説が救いであり神様だったのだろう。
相手の才能や長所に惚れ込み神格化するところから始まる恋愛もあるのだと思う。だがそれだけで関係を長く続けていくことはできない。
完璧な人間などいない。
日常生活を一緒に過ごしていく中で、少しずつ相手の欠点を知っていく。それも含めて相手の全人格を受け入れようと努力し続けることが、普通の人間関係なのだと思う。
梓は完璧主義が過ぎた。
母親から虐待され少しのミスも許容されない環境で育った梓は、不完全さを許せなくなっていたのだろう。
一方、遥川はプライドが高すぎた。
若くして成功したことで、才能が摩耗することに恐怖を感じていたのだろう。
お互い惹き合いながら、破滅の方向に向かわざるを得なかったのは悲しい。
二人には自分と相手を「許容する」ことが何より必要だったのだと思う。