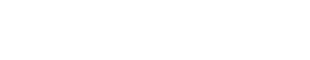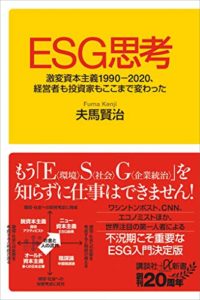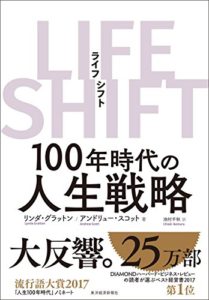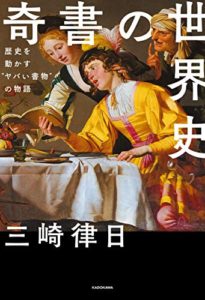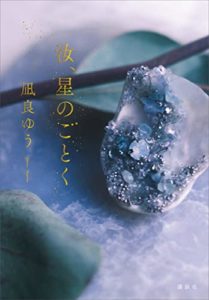ずるい考え方 ゼロから始めるラテラルシンキング入門
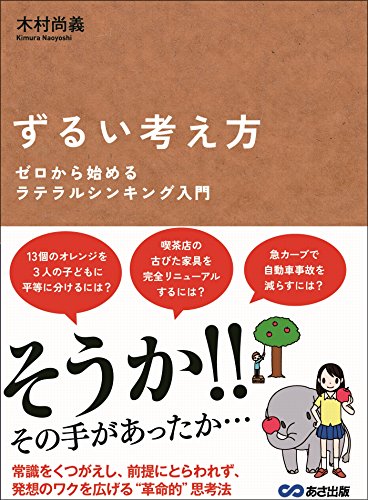
こちらで購入可能
要約
常識に捉われない自由な発想で、最短ルートで問題解決する「ラテラルシンキング」を紹介。
ラテラルシンキングとは
論理的に思考を深める「ロジカルシンキング」に対し、水平方向に発想を広げるのが「ラテラルシンキング」だ。
唯一の解はなく、問題解決できれば全て正解。
・あらゆる前提から自由になる
・前例のないものを生む
・最短での問題解決
・時間、お金などコストの削減
というような特徴がある。
ラテラルシンキングとロジカルシンキングは相互補完の関係にある。
なぜラテラルシンキングが必要か
「唯一の正解」を求める学校教育ではロジカルシンキングが主となるが、新しものを作り出すときには常識に捉われない自由な発想が求められる。
IT関係など変化の速い業界では特に重要となる。
ラテラルシンキングの事例
自動改札は乗換時の運賃計算で時間がかかるが、高速なコンピュータを載せる予算がない。
→ 改札気を長くして時間を稼いだ。
イベントで販促冊子を受け取ってもらえない。
→「一人3冊まで!」と大声で叫んだ。
ラテラルシンキングに必要な力
①疑う力
「~であるべき」という常識を疑う。
・「お茶は無料」という常識を覆して、缶入り、ペットボトル入り茶の市場を作り出した。
・事故防止には設備が必要という常識を覆し、センターライン、ガードレールを無くし事故を減らした。
外国人や異世代の人、異業種の人との交流は常識を疑う力を磨く。
②抽象化する力
「物事の本質」を抽象的に理解することでその置き換えを考えることができる。
・ヘンリー・フォードは、人々が「より速い馬車」を求める時代に、要求の本質は「安く速く移動できること」だと見抜き、高性能な自動車を普及させることを目指した。
例えば「新聞紙の利用法を30種類考える」などのエクササイズが本質をつかむ練習になる。
③セレンディピティ(偶然の発見)
偶然を偶然として無視しない、偶然を何かに結び付ける力。
・航空機レーダーの研究から電子レンジが生まれた。レーダーの実験でチョコが溶けるのを偶然として片づけず、追求しようと考えた。
・お菓子の袋に入れる脱酸素剤の研究で、鉄粉は過熱し失敗と判断されたが、開発者はカイロへの転用を思いついた。
最小の力で最大のリターンを得るには
人間は本質的に怠け者で楽をしたい。最小の力で最大のリターンを得るのが理想。
・他人の力を利用する
トムソーヤーが楽しそうにペンキ塗りをして人にやらせたようなやり方。
・作業を組みわせる
フォークリフトに重量計を組み込んで、重さをはかる一工程を省略したケースなど。
・楽をする権利を買う
アドバルーンの監視というバイト料は低いが比較的楽な仕事を選び、お金を稼ぎながら勉強したケースなど。
相手の力を利用する
強者と直接ぶつかるのではない戦い方をする。
・コバンザメ型
大きな存在に付いていくことで利益を得る。大きな存在の方は得るモノも失うモノもない。自動車メーカーについていくティア1カー用品メーカーなど。
・寄生虫型
大きな存在に付いていき、その利益をかすめ取る。人気店の行列に耐えられない人を狙った出店など。
・ヤドカリ-イソギンチャク型
イソギンチャクは移動手段を得、ヤドカリは毒イソギンチャクに守られる。お互いに利がある関係。
ブランド野菜と有名レストランの関係で、「あのレストランで使われている!」という売り文句と「あの野菜を使っている!」という売り文句の両方に価値があるような場合。
異質なものを組み合わせる
ゼロから新しいものを発想するのは難しいが、既存のモノを組み合わせて新しい価値を見出すことは比較的やりやすい。
・容器の改修に困っていたアイスクリーム屋が、隣で売っていたエジプト菓子を使いコーンを作ることを思いついたケースなど。
先の先を読む
目先の利益を追求するのでなく、最終的にベストの結果を得ることを考える。
・水源から水を運ぶのにバケツでの運搬ですぐさま利益を上げるのでなく、時間と費用を投資し水源からパイプを引く工事をして安定的に安価に運搬する仕組みを作るなど。
・エジソンも白熱電球の改良に成功した際、電球を作る工場より、電力会社への投資を考えた。
無駄なものを捨てない
無駄があってこそ新しい結びつきが生じる。
・アリの集団では必ず2割は統率の取れないさぼりアリとなる。勤勉なアリだけを抜き出して新たな集団を作っても、そのうちの2割はさぼりアリになる。
さぼるアリは平時には役に立たないが、新しいルートの発見や、行き詰まった状況の打破に貢献するため、組織全体のためには必要。
マイナスをプラスに変える
「時間がない」「予算がない」などマイナス要素を発想の転換でプラス要素に変える。
・ カステラの端っこなど形の悪いものは「訳アリ品」として売ることで、買い手側も「味に問題ないが見た目のため安い」という理由付けができるため売りやすい。単純に値引くより敢えて「訳アリ品」として売るケースも増えている。
・「元暴走族の塾講師」「元暴力団の牧師」など過去のマイナスイメージを「道を踏み外したからこそアドバイスができる」というように逆利用する。
・阪急電鉄のできた当時、沿線は辺鄙な場所だったが、何もないことを「静かで環境がいい」としてメリットに転換し住宅販売につなげた。
また競合路線と比べて人気がなく客が少なかったが「空いていて快適」と魅力を打ち出した。
感想
「ラテラルシンキング」の説明が簡潔で分かりやすいし、実践事例やトレーニング方法も紹介され具体的にイメージしやすい。
「新聞紙の使い方30種類」とか「異質なものの組み合わせアイディア」とか考えていると中々楽しい。
ラテラルシンキングには発想の「飛躍」が必要で、過去の常識に縛られてはいけないが、過去の事例をたくさん知っておくことは「新たな結びつきの発見」につながるのだろう。
短いが内容が詰まった良い本だった。