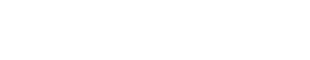彼岸花が咲く島

こちらで購入可能
生きることはは変わること。
多様性を抱えるから迷う。でも変わっていけることが強さなんだと思う。
おそらくは数十年から数百年後、いわゆるポストアポカリプス(終末後)の話。
舞台になっているのはどうも与那国島っぽい。古くから琉球、台湾、日本、中国の文化が交差してきた場所で、「民族・文化」と「男女の性差」の2つの「分断」を軸に物語は展開する。
とくに「民族・文化の分断」に対する作者の見方には共感を覚えた。
主人公の少女「宇実」の故郷「ひのもとくに」は、異民族を排斥するようになった。宇実も「ひのもとくに」から追放されて島に流れ着いた。「ひのもとくに」で使われる「ひのもとことば」は、ひらがなとカタカナのみで構成されている。漢語を一切排除した「大和言葉」で、民族文化の純粋性を追求したものだ。
これに対して島で使われている言葉「ニホン語」図太く柔軟だ。日本語と中国語が混じったような言葉だが、イキイキとして地に足のついた生活感があって気持ちいい。この「ニホン語」自体が本作品の中心で、民族の純粋性に対するアンチテーゼになっているのだと感じる。
ここでちょっと自分自身の話。
私はつい最近日本に戻るまで、都合10年以上海外で暮らしていた。社会の中の少数派「ガイジン」としての生活を経験している。
その経験を通し感じたのは「国単位での傾向の違いはあるけれど、個人レベルのブレの方がでかい」ということだ。個人の生活レベルでは「どこの国に住むかより、どんな人と出会うか」が重要だ。
例えば「日本人よりアメリカ人の方が外向的だっていうけど、私の知っている外向的な日本人は、私の知っている内向的なアメリカ人よりずっと外向的」ということ普通に起こる。「アメリカ人は外交的」というステレオタイプな偏見に惑わされず、目の前にいる「シャイなアメリカ人」の本質を見て付き合うことが大切なのだ。
国や大企業など巨大な組織規模でみれば、「傾向の違い」が大きな違いになっていくが、個人レベルでは「中央値の差より、偏差内でのばらつき」の方がでかい。そして、中央値の差は、個人単位のばらつきと比べれば微々たるものだ。
その実感から「国レベルのわずかな傾向の差にこだわることに、どれだけの意味があるのだろう」と思うにいたった。逆にみると「国レベルのわずかな違いも許容できない社会は、個人レベルの多様性にも不寛容になってしまうのでは」という不安だ。
一方、私が最近まで暮らしていたオランダは、とくに多様性を受け入れる柔軟性が高い場所だった。
例えば自分が働いていた事務所では、従業員は40人程度だったが、国籍でいうと19カ国の出身者で構成され、極めて雑多な雰囲気だった。街に出ても現地語であるオランダ語と共通語としての英語が同レベルで使われていて、自分が外国人であることを強く意識せずに生活できた。
中にはアジア人に偏見を持つ人もいたし、衝突することもあった。それでも衝突のあることを前提とした社会の仕組みは「頑強」だと感じている。
本書で描かれる「ニホン語」のような「雑多なものを節操なく取り込んでいく強かさ」を好ましく感じたのは、自分の経験と繋がっているのだろう。
物語の舞台となった島は、大国に挟まれた不安定な場所だった。でもそれは特殊状況ではない。情報面でも、実際の人やモノの流れでも、グローバル化の流れは止まらない。全ての人の生活が世界中の人々との関係の上で成り立つようになってきている。
その中では、多様性を受け入れ、変化を受け入れていく「したたかさ」が強力な武器になっていくのだと思う。
あらすじ
とある島の彼岸花の咲く浜辺に、傷だらけの少女が流れ着いた。
島に住む 游娜(ヨナ)は、少女が海の向こうの楽園ニライカナイから流されて来たのだと信じ、家に連れ帰り看病する。
意識を取り戻した少女は記憶を失っていた。游娜は海からやってきた彼女を宇実(ウミ)と名付けた。
島を取り仕切り歴史を伝えるのは「ノロ」と呼ばれる女性たちだった。
その島で使われる言葉は、日本語と中国語が混じったような「ニホン語」で、ノロたちの間では、現代日本語に近い「女語」と呼ばれる言葉も使われている。
ノロたちは船で定期的に「ニライカナイ」に渡り、宝物を持ち帰ってきた。島で生産できない貴重な物資がもたらされ、その配分などもノロが全て取り仕切っている。島に貨幣はあるが物々交換が主で金融的な活動はなく、経済が実際の必要を超えることはなかった。
家族や結婚の観念がなく、男女間に子供が生まれると「島の子供」として2歳までは一緒に育てられる。2歳からは血縁を持たない「オヤ」が養育し、成人すると家を出ていく。その後は、一人で暮らすのも誰かと一緒に住むのも自由だった。
宇実は「ひのもとことば」と呼ばれる言葉を話した。「ひのもとことば」は現代日本語から漢語を排除した「大和言葉」に近く、それだけでは伝えられない抽象観念などは、カタカナ英語で表現する。島の「女語」と「ひのもとことば」が似通っていたため、宇実はノロを目指し女語を学んでいた游娜と意思疎通することができた。
宇実の常識と大きく異なる島での生活に戸惑うが、游娜たちに助けられゆっくりと島の生活に馴染んでいった。
宇実の傷が癒え、島の祭り(マチリ)が終わった頃、游娜は宇実を連れ ノロの長「大ノロ」に会いに行き、宇実の今後について相談した。
大ノロは最初「島の人間を守るため、よそ者を受け入れることはできない。島を出ていけ」と言ったが、游娜の説得に大ノロは「来年の春にノロとなる試験に合格すれば、島に残ることを認める」と譲歩した。
游娜と宇実の友人 拓慈(タツ)も、島の歴史を知りたいと願っていたが、男であるためノロとなることが認められなかった。「よそ者」なのに、女だからというだけでノロとなる資格を得た宇実を妬み、一時」険悪になる。だがやがて拓慈は自らの狭量さを謝罪し、游娜たちは「ノロになったら島の歴史を拓慈にも教える」と約束した。
だが、無事ノロとなった游娜と宇実が聞いた島の歴史は驚くべきものだった。
ニライカナイとは何なのか、男がノロになれないのはなぜなのか、大ノロが宇実を排除しようとしたのはなぜなのか。
「歴史」を知った游娜と宇実の心は揺れ動く。