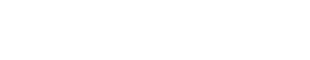楽園とは探偵の不在なり

こちらで購入可能
特殊設定ミステリ ✖️ クローズドサークル連続殺人
「2人を殺したら地獄行き」のルール下で起きた連続殺人の謎を解く
ある日突然地上に降臨した「2人を殺した人間を地獄に引きずり込む天使」は、世界から大量殺人をなくした。だが、天使が強制的に持ち込んだルールは「1人なら殺してもいい」という解釈も生みだし、「どうせ地獄行きなら、たくさんの道連れを」と考える人も現れた。
この話を聞いて、「お迎えの時間の遅刻に罰金を設けた保育園で以前より遅れる人が増えた」というエピソードを思い出した。「迷惑にならないように」という道徳の問題が、「お金で時間を買う」という経済のルールに置き換わり、「お金を払えばそれでいい」と捉えられてしまった。ルールがあることで「ルールに従った行動は許される」と感じる。強制力は思考を停止させるのだ。
逆に「ルールや強制力として姿を現さないもの」の方が、内側から湧き上がる行動を引き起こす力を持つ。実際そこには見えないもの「不在が一番場所をとる」。
本書では「ルールに縛られた人たち」と「自分の中にある正義を信じた人たち」の対比が描かれる。
島に集まった常木の「同盟者」は、ルールの裏をかいて大金を稼いだ。だが彼らは満たされない。ルール(=天使)に過度に依存したり、逆に嫌悪したりして、常に不安を抱えている。
一方で、主人公である探偵青岸のかつての仲間たちは、自分自身の思いで動いていた。「困っている人は助けなきゃ」レベルの、練られていない雑な正義だが、それでも自分の心に従っていた。
客観的には彼らの結末は不幸であったかもしれないが、彼らの人生が満たされ幸せであったことは間違いない。
天使を遣わした神の真意は人間には理解できない。理不尽に見えても従うしかない。
テッド・チャンの『地獄とは神の不在なり』は、「神は理不尽だ、それでも、だからこそ信仰が人を救う」と伝えている。
この『楽園とは探偵の不在なり』は、「神は理不尽だ。それでも、だからこそ、考えることを諦めてはいけない」と伝えようとしているのだと思う。
あらすじ
ある日突然地上に「天使」が降臨した。
天使たちは「2人以上殺した人間」を問答無用で地獄に引きずり込む。コウモリのような姿は「悪魔」に近かったが、人々は自然にそれを「天使」だと認識していた。
頭部が削られたようになっていて顔がなく、喋ることも感情を表すこともない。対象となった人を地獄に落とすとき以外は、人間には何の干渉もせず、公園の鳩のように、ただ漂っているだけだった。
天使の降臨は犯罪を減らし戦争をなくした。
一方で「1人までなら殺すことは赦された」と信じる確信犯による殺人や、「どうせ地獄行きなら、2人といわず、できるだけ多く道連れにしよう」という大量殺人狙いの巻ぞれ自殺も発生した。
主人公の探偵の青岸焦にはかつて仲間たちがいた。彼らは、大量殺人巻き添え自殺に使われる新型爆弾の流通経路を追っていた。その途中、彼ら乗った車が、大量殺人を狙う自殺者の爆弾に巻き込まれ、青岸以外の全員が死んでしまう。
失意に沈む青岸は細々と探偵業を続けながら、仲間たちを助けられなかったことを悔やんでいた。
仲間たちに救いを与えなかった天使たちを憎み、彼らが「天国」に行くことができたのかを知りたいと願った。
そんな青岸を、大富豪の天使マニア常木王凱が天使の集う島「常世島」に誘う。島には実業家の争場、天国研究家の天澤、記者の報島、代議士の政崎も呼ばれていた。
屋敷には、専属医師の宇和島、メイドの蔵早、料理人の大槻、執事の小間井も常駐し、さらに記者の伏見も、常木たちの悪事を暴こうと島に潜入していた。
天使の流失を嫌う常木は船の発着を制限していたため、彼らは「クローズドサークル」となった島に滞在することになる。
島の主である常木の死を皮切りに、次々とゲストたちが死んでいく。
「2人以上を殺すと地獄に堕ちる」この世界で、どうやって「連続殺人」が行われたのか。
「探偵であること」から逃げていた青岸は、その謎の解明に取り組んだ。