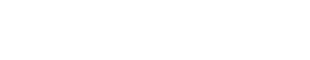君の話

こちらで購入可能
あらすじ
天谷千尋の両親は虚構を愛していた。
当時はナノマシンを使い記憶を操作する技術が発展し「義憶」という偽りの記憶を脳に焼き付けたり、忘れたい記憶を消すことが広く行われていた。
千尋の両親は現実世界よりも義憶の中の世界を愛し、現実世界での千尋を放置していた。愛し愛されることを学ばなかった千尋は人間関係の構築に苦労し孤立した思春期を過ごした。
大学生になった千尋は「器がなければ空っぽも成立しない」と考え、少年時代の記憶を消す処置を受けることを決意した。だがクリニックの手違いで、記憶を消す「レーテ」ではなく、青春時代の楽しい記憶を作る「グリーングリーン」が処方されてしまう。
千尋は「完璧な幼馴染」である夏凪灯花との思い出を手に入れる。彼がこれまでの人生で得ることのできなかった、家族であり友人であり恋人でもある灯花との思い出は彼の心を満たしていった。
ところがある夏祭りの夜、千尋は灯花に出会う。
千尋はレーテで灯花の義憶を消そうとするが思い切れず、彼女に強い執着を感じていることを自覚する。混乱し酔いつぶれた千尋がアパートの自室に戻ると、そこには 灯花 がいた。
灯花は「自分は千尋の幼馴染だ」と言うが、千尋はそれが義憶であることを認識している。中学時代の知り合いに確認してみても「夏凪灯花」という人間が実在しなかったことは間違いない。
それでも、自分は灯花であると主張する彼女は何者なのか。
千尋は彼女は自分を陥れようとしている詐欺師だと考えながらも、どうしようもなく惹かれてしまう自分に戸惑う。
ある夜、灯花がかつてのように喘息の発作に苦しんでいると思った千尋は彼女の部屋に向かう。彼女の無事をみて心から安堵した千尋は、自分が彼女を受け入れていることを認めていく。
千尋は灯花と義記の続きのような夏休みを過ごすが、灯花は突然「しあわせだった」と一言書き残して消えてしまった。
灯花の両親は相手の立場に立って考えることができなかった。
灯花は幼いころから喘息にかかっていたが、良心その苦しみを理解することはなく「他人様に迷惑をかけないよう」外出することなく過ごしていた。
そんな環境で灯花は卑屈で自罰的に育ち、学校では孤立して過ごしていた。
感想・考察
三秋縋さんの話では、理性のコントロールや自分の自我を信じられなくなるような状況が良く描かれる。本作の義憶だったり、「恋する寄生虫」では寄生虫に恋愛感情を操られたり。
三秋作品では「自我への疑い」がデフォルメされているが、現実世界でも人間の意志が本当に主体的にコントロールできているのかは分からない。脳科学や認知心理学では「自由意思」の存在を強く疑っている。
でもそれでも「私は自分の選択で人生を作ってきた」と言えるから生きることは素晴らしい。
自分の記憶、自分の意識に疑いを持ちながら、それでも「これを選ぶ」という意志で未来をつかむ。客観的には不幸に見えても、本人にとって最も幸せな結末を選んでいる。
そういうカッコよさが三秋縋さんのお話にはある。
本書は三秋作品の集大成的な感もあり、ぜひ一読をオススメしたい。