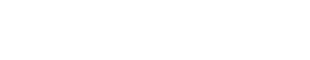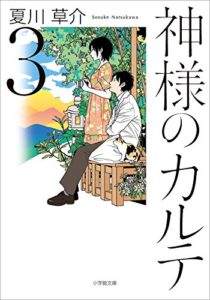勿忘草の咲く町で ~安曇野診療記~

こちらで購入可能
「医療は今、一つの限界点に来ている。『生』ではなく『死』と向き合うという限界点だ」
終末医療について考えさせられる話です。
感想・考察
シンプルにいうと「身寄りのない回復の見込みもない老人に医療コストをかけるな」という提言で、終末医療に対するかなり過激な提言だ。
医療リソースの問題、患者と社会の繋がりの問題という二つの側面から、終末医療の在り方について問題提起している。
医療リソースの問題は、作者が「神様のカルテ」シリーズでも提言していたものだ。地方都市の病院で医師が不足し、過酷な勤務状況になっていることを訴えている。本作では特に「回復の見込みのない老人への対症処置のため、将来のある若い患者が犠牲になっている」という問題がクローズアップされている。
医療リソースの問題は、一人の医者や、一つの病院単位では解決のできない問題で、その中で真摯に奮闘する姿勢と、その無力感が本書のテーマの一つだ。
リソースの問題を解決するなら、もっと大きく世界的な単位での動きが必要なのだろう。高額過ぎる医学部の学費に対する補助などで医者の人数を増やしたり、RPAなども活用し一般起業のように業務の効率化を徹底したりすることは可能だと思う。
だが、投資に対する見返り」のレベルで考えると「高齢者の延命から得られるリターンは何か」という話になってしまうので、ドライバとなるのは功利的な考えではなく、道徳や倫理になるのだろう。
そうすると、著者が提起している2点目「患者と社会の繋がり」が重要になる。
本書では「指導医の指示を無視し、家族が死に目に会えるよう数時間の延命を行った」エピソードや、「本人は延命を希望しないが家族から大事にされている患者」と「認知症で本人の意思は確認できないが、家族との関係が切れてしまっている患者」を並べて考えさせるエピソードが出てくる。
研修医の桂が出した判断は「根が切れてしまっている=社会とのかかわりが失われてしまっているならば、回復の見込みがない高齢者に延命措置を施す必要なない」というものだった。
今の医学は病気による症状は抑えられても、機能を回復させるのは人間自体の力に頼っている。「誤嚥性肺炎」の症状を抑えることはできても「飲み込む力」を回復させることはできない。自己回復力の低下した高齢者に延命の治療を施す意味は「ただ生かすだけ」ということになってしまう。
それでも、親しい相手がいれば、その人にとっても患者本人にとっても「生きている」ことに意味はあるが、「根が切れて」しまった患者であれば「誰のため、何のため生きているのか」が分からない状態だ。
心身が健康であれば何歳からでも社会とのつながりを作ることはできるだろうが、回復の見込みがない病を抱えているとそれも難しい。
桂の出した判断は非情に残酷に感じるが、真摯に考えた一つの結論として理解はできる。作者も「この判断が正しい」と主張するのではなく「思考停止に陥らず、自分の頭で考えることが大事」だと言っている。
死の問題からは目を背けてしまいがちだが、逃げることはできない。
という感じで結構重くて暗いテーマだが、一方で若い看護師と研修医の恋愛ストーリーという明るい面も描かれている。
安曇野で巡る四季が命の循環を暗示しているようで、新しい命が芽吹く春の風景に救われたような気持になった。
あらすじ
安曇野を望む梓川病院で働く看護師の月岡美琴は、研修医の桂正太郎と出会う。実家が花屋である桂に「鈴蘭とサンダーソニアの間違い」を指摘されたり、当初はつかみどころなく感じていたが、患者に真摯に向き合う姿勢を見て徐々に惹かれていく。
桂は患者の平均年齢が86歳となる梓川病院で高齢の患者に対処していた。「死神」と呼ばれる指導医の下では、無理な延命はしない姿勢を見せられ、医療の理想と実態の乖離に悩む。