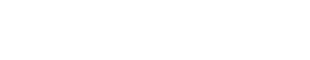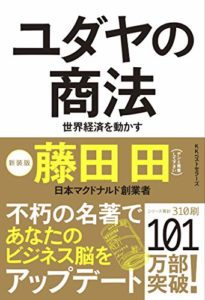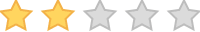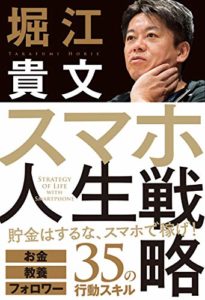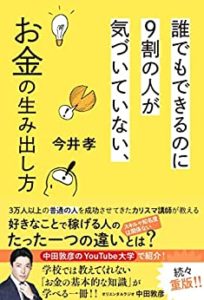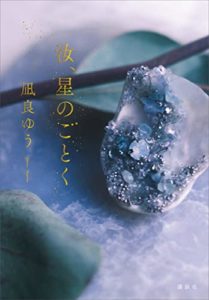世界を見てきた投資のプロが新入社員にこっそり教えている驚くほどシンプルで一生使える投資の極意
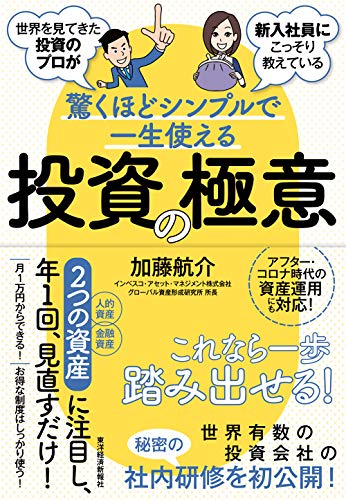
こちらで購入可能
要約
「金融商品は人生をバランスよく幸せに生きるための便利な道具」
外資系金融企業の先輩が新入社員に講義する形式を取って、投資について解説してく。
- そもそも「投資」ってなんですか?
投資が成長を促し、将来のゆたかさにつながる。そのサイクルが拡大することでより良い世の中が作られる。
投資とは別に金持ちだけが行うものではなく、子供の教育や飲み会での懇親など、将来の成果のために先に行う行為が全て投資だといえる。個人、企業、国家など、さまざまなレベルで行われている。
- 「人的資産」という考え方
「これからお金を稼ぐ力」が「人的資産」
健康で働く意思を持っている人であれば、それだけで数億円の人的資産を持っているといえる。
投資を考えるときは、お金という形の「金融資産」だけでなく、人的資産とのバランスを取る必要がある。
「人的資産」を考える上で大切なのは、心身の健康。
- まずは自分に「正しく投資」
社会とは「属する人の人的資産のかたまり」といえる。
それぞれが自分の人的資産を拡大させるため投資をすれば、世の中全体が豊かになっていく。
長期的に見れば「人的資産の運用」のほうが「金融資産の運用」より重要だといえる。
自分の人的資産を増やすための「自己投資」を考えるとき大切なのは
①先々に必要とされるスキルであること
②希少性のあるスキルであること
の2点。
- 日本人のための「正しい分散投資」
「分散投資」を考えるときは「人的資産と金融資産」のバランスを考えることが重要。
あなたが日本人で日本で給与所得を得るつもりなら、あなたの人的資産は「日本経済の動向」に深く関わってくる。
リスク分散を考えるのであれば、金融資産は日本の経済動向に影響されない部分にも回すべき。
日本の企業で働き、投資も日本株などに偏っているとすると「日本への超集中投資」という状況に陥っている。
- 日本の「本当の姿」
日本人が生活する上では日本はとても良い環境だといえる。
とくに
①安全
②健康
③サービス
④インフラ
⑤文化
の5つの側面でバランスよく高いレベルにいる。
一方でここ数十年の経済成長や賃金推移などをみると「ゆたかさ」の面では徐々に力を落としている。
日本の経済成長が著しかった昭和時代であれば、「人的資産」、「金融資産」の両方を日本に集中投資することが有効だったが、経済のグローバル化が進む中、日本に偏ったポートフォリオを修正していく必要がある。
- バランスを取るという考え方
日本の雇用状況は安定している。
日本に住んでいて健康であれば、それだけで「超安定資産」を持っているといえる。
①日本資産と海外資産のバランス
②安定資産と成長資産のバランス
を考えた場合、日本に安定した人的資産を持っているのであれば「海外に成長資産を持つ」のがよい。
とくに欧米系の大企業では、経営者と株主の利害が一致するため、ダイレクトに企業価値を上げる経営が行われるケースが多く、リターンの高さが期待できる。
- 「株式投資」ってそういうことだったんだ
主な投資先は、国に投資する国債と私企業に投資する株式がある。
株式は、とくに新規会社の立ち上げや事業拡大などを支援する意味合いがある。
- 日本大企業経営の「最大の問題」
大企業の場合、従業員やサプライチェーンなど影響範囲が広いため社会的責任も大きい。企業活動を監視する仕組みが必要。
民主主義政治で権力者をモニタリングする仕組みが「選挙」なのと同じように、企業活動をモニタリングする仕組みが「株式」であるといえる。
とくに欧米系企業では経営者が株式で給与をもらうケースが多く、短期での売買は制限されてるので、経営者は長期的な会社運営に責任を持つことになる。
一方日本では経営者でも現金で給与をもらうケースが多く「自分の任期を無事に過ごせればいい」という考えになりがちで、投資家と利害関係が一致しない。
- いいファンドマネージャーの3つの基準
個人で企業の活動をモニタリングするのは難しい。
「投資信託」という形で集めた資産を運用し、間接的にモニタリングを助けるのが「ファンドマネージャ」と呼ばれる仕事。
いいファンドマネージャーの条件は以下の3点。
①ロングターム:長期視点を持っているか
②ボトムアップ:事業そのものをみているか
③インセンティブ:投資者と同じ利害関係にあるか
いいファンドマネージャーは企業経営を監視し、より良い社会を築くことを助ける。
- 世界の株の利回りがいい5つの理由
日本株と比べて世界の株の利回りが良い理由は以下の5点。
①経営者が株現物給与のため投資者視点
②経営陣の目標設定が高い
③成績の良くない企業が株式市場から脱落する仕組み
④長期視点ボトムアップ型ファンドマネージャの存在
⑤市民の株式投資に対する理解の高さ
会社経営者と投資家の利害が一致しているのが大きいと著者はみている。
また、市民が投資に参加することが、経済社会が監視されることにつながると考え重視している。
- 正しい投資の3大ステップ
①人的資産と金融資産を合わせた「真の自己資産」のバランスを把握する
②バランスを意識しながら投資を実行する
③年に一度見直しを行う
人的資産と金融資産両方をみる視点が大切。
また、頻繁にチェックして気にし過ぎると短期的なブレに惑わされてしまう。株は本質的に長期で成長するものだから、チェック頻度は年に一度くらいにして細かい値動きを見ないようにする。
- 「アクティブファンド」と「パッシブファンド」
株価指数などをそのまま受けて作るインデックス型やETFなどは「パッシブファンド」と呼ばれる。
一方、ファンドマネージャーが個別企業を調査して組むのが「アクティブファンド」手間がかかる分、手数料は高くなる。
過去のパフォーマンスを見ると長期的には「パッシブファンド」の方が幾分利回りが良い。
初心者はパッシブファンドから手を出す方がわかりやすい。
しかし「企業経営の監視」という観点からは、アクティブファンドの存在も大切。
著者は、最終的には、アクティブとパッシブを半々で持つことを薦めている。
- 「円高」と「円安」の考え方
長期でみた為替は、国の相対的な豊かさを表す。
長期的な円高は日本経済が豊かになったことを示している。
輸出が主たる外貨獲得手段だとすると、短期的には円安は競争力の低下につながるが、一方海外からの材料調達などがしにくくなり、長期視点ではデメリットも多い。
為替のリスクをヘッジするためには「生活基盤が場所と、資産運用先の通貨を同じにしない」ことが大切。
- リスクとリターンの関係
必ずしも「ハイリスク・ハイリターン」「ローリスク・ローリターン」であるとはいえない。
リターンは「長期の利回り」、リスクは「短期の値動きの大きさ」と捉えるなら、必ずしも長期の成長性と短期の値動きリスクは連動しない。
金融商品の長期の利回りは「現実世界上の理由」で決まっていて「金融市場上の理由」ではない。
- 年代別の投資アプローチ
日本に住んでいて日本で稼げる現役世代は、日本に人的資産を集中させているので、金融資産は「海外株式に積極投資」すべき。
リアイア世代も、年金が主たる人的資産だと考えると、やはり日本に集中投資しているといえる。金融資産の投資先としては世界バランス型が適している。
- 最後のアドバイス
①金融相場の下落は必ず訪れるが「その時期も我慢して投資を続ける」ことが大切。
②早い時期に投資を始めれば少額でも大きな資産を積み上げられる。NISAや確定拠出年金など税制優遇の仕組みを活用し、月数万円からでも投資に回すべき。
感想
投資の話で「人的資産」と「金融資産」のバランスを説くのは面白い。
確かに、日本人であれば「働いて稼ぐ」ことは日本の状況に依存しがちだから、最大の財産である人的資源は「日本に集中投資」しているといえる。
私など海外生活が長いけれど、日系企業の駐在員という立場なので、日本経済の動向に影響を受けることに変わりはない。
日本以外の国に根を下ろして生活している人もいるが、その人はその国に集中投資してしまっている。
ナショナリズム的な「自国主義」が高まることがあっても、長期的傾向として経済活動のグローバル化は止まらないだろう。経済が一つの国の中だけでバランスする時代ではなくなってきている。
そうなると、自分が持つさまざまな資産を、複数の国に分散させておくことは、リスクヘッジとして有効なのだと思う。
日本人にとって直接的な海外投資は敷居が高い。
本書は外資系ファンドマネージャが書いたものだし、ポジショントーク的な部分は必ずあるのだろうな、とは思う。
とはいえ、日本の極端な物価安はバランスを欠いている感があるし、海外に分散投資すべし、という提案は受け入れられるものだ。