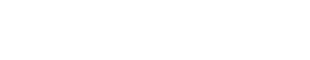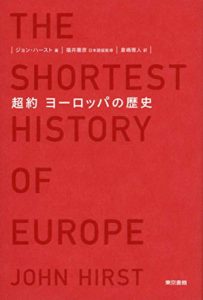君主論

こちらで購入可能
慈悲深く、信義を守り、人間味があり、誠実で、信心深いことは素晴らしい。
でもそれを「常に守る」のは有害だ。
本書の意図
本書は16世紀初めのイタリアで、ニッコロ・マキャベルが著した政治思想書。
マキャベリは、徹底的に「現実」を見ている人だった。
例えば「君主が全ての面でいい人なら理想的。でもそんなの無理で、ときには悪いことをする必要もある」という。
今の私たちからみれば「まあそうだよね」という内容だけど、キリスト教道徳が支配的だった当時の状況下では「相当にラジカルな発言」と受け取られたようだ。
「人の道にもとる内容だ」として一時は発禁処分にされていた。
さらに現代に至っても「マキャベリズム」という言葉は「目的のためには手段を選ばない、冷酷さ、狡猾さ」として使われている。
実際、マキャベリにそういうところがあったのだろうとは思う。
ただ、書かれている内容を冷静にみるとその根本には、当時不遇な状況にあったイタリア人民の「痛みを最小限にするにはどうすればいいのか」という視点があることに気づく。ありえない理想論ではなく、現実に際した最適解を探そうという試みだ。
本書はマキャベリが「君主」に捧げる内容だったが、実際には人民に対しても「心構え」を問いた思想書でもあったのだと思う。
君主論の思想を現代に役立てる
君主論は現実的な視点で書かれている。
とはいえ、500年以上前の本だけあって具体的な内容はさすがに時代遅れだ。例えば騎兵と歩兵の運用など、軍事論として現代に通用するものではない。
それでも、組織や人間心理についての洞察は深く、エッセンスの部分は今の言葉に翻訳して役立てられると思う。
役立てられるポイントはたくさんあるが、個人的に興味を持った下記の5点に絞って、「現代だったらどういうこと?」という視点で考えてみたい。
1.新たに君主になった地での振る舞い方
2.避けられない悪事は短く最小に
3.自前の軍隊を持つ
4.人民が一番大切
5.良い資質だけを持つのは不可能
以上の5点だ。
新たに君主になった地での振る舞い方
マキャベリは新たに獲得した地を保持する方法として、以下の3つから、どれか一つの手段を選ぶべきだという。
①そこにあったものを全て破壊すること
②自らそこに移り住み一体となって統治すること
③少数者による政府を打ち立てて支援すること
の3つだ。
人々を馴染んでいたものから引き離すのは難しく、新しいものを信じさせるのも難しい。
「人間というものは、確かな経験が生まれるのを目にしない限り、新奇な事柄を事実とは信じないもの」であり「変化に抵抗する勢力は党派的激情をもって攻撃してくるのに、味方となるものには熱意がない」のだという。
だから、新参者の立場でその地を治めていくには「元々そこにあったものを完璧に壊して自分色に染めてしまう」のが手っ取り早い。
ただそのやり方では多くのものが失われてしまうし、現実的には不可能なことも多いだろう。
それが難しければ「自分自身がその地に入り込み、人民と一体となって内側から改革していく」もしくは「その地の中の少数者を支援して統治改革を行う」のが良いのだとする。
自分が中に入り込むのであれば多数者となる人民を味方につけること、直接入り込めないのであれば、自分の敵対勢力とならない程度の少数者に自分の意に沿った統治を行わせる、ということだ。
どちらのケースでも「大量の敵と直接対峙しない」というのがポイントになる。
ただ最後の「少数者による政府を打ち立て支援」というのは匙加減が難しそうだ。
実際、アメリカがタリバンにしっぺ返しを食らっているのをみると「少数」という侮りは恐ろしいのだと思う。
避けられない悪事は短く最小に
「国家を奪い取るにあたっては、成す必要がある気概を検討し、繰り返さないよう一気に行う」べきだという。
一方で人民に恩恵を与えるときは「よりよく味わうため、少しずつ」なされるべきだとしている。
暴力を行使して既存勢力を排除するのは短期間に集中すべきで、長期にわたると自分自身も統治される人民も疲弊してしまう。
現代において「旧勢力は皆殺し」のような極端なことは少ないと思うが、「力の行使には副作用が大きい、できるだけ短期集中すべき」というのは変わらない。
自前の軍隊を持つ
「傭兵軍はやる気のなさ、外国援軍はその力量が危険要素」だといい、傭兵や外国の援軍に頼らず、自前の軍隊を持つべきだと強調している。
自前の軍隊以外に依存すると「弱すぎれば頼りにならず、強すぎれば裏切りを警戒しなければならない」ということだ。
直接的な軍事論としては時代遅れだが「何かと対決するときに心構え」としては、現代でも通用する部分があるように思える。
例えば、色々と策を巡らせて周囲を味方につけたとしても、自分自身の力量が不十分であれば、その関係はいつかバランスを失い、相手に飲み込まれてしまう。
また、実力に自信のない人は「自分と同程度に弱い人」と連むのが楽だが、残念だ柄あまり頼りにはならない。
「自分自身の力量をあげるから、強力な相手とも対等な関係を築くことができる」ということなのだろう。
とはいえ、現代では戦争のように「一度の敗北が死につながり再チャレンジできない」という状況はそう多くない。格上の相手に翻弄されることがあっても、トライアンドエラーで経験を重ねていく方が「自分自身の力量を上げる」近道なるのでは、とも思う。
人民が一番大切
君主論は君主に統治の心構えを諭す本だが、マキャベリ自身は君主制を必要悪ととらえていて、むしろ共和政が理想だと考えている節がある。
「人民の支持で君主になったものは、人民を味方につけておかなければならない。人民に逆らって貴族の支持で君主になったものは、何よりもまず人民の支持を獲得するように努めなければならない」という。
君主は中間層にあたる貴族よりも最多数である人民を第一に考えるべき、という話が繰り返されている。
現代でも、長期的な生き残りを考えるなら
「上を見ている上司」より「部下の支持を得た上司」の方が強いし、
「株主を機にする会社」より「従業員、顧客を気にする会社」の方が強い。
マキャベリが封建制度、君主制の元でこういう思想に思い至ったことが興味深い。
良い資質だけを持つのは不可能
マキャベリは「君主が良いと思われる資質をすべて備えているなら賞賛に値するが、実際には不可能」だと考える。場合によっては「悪徳」とされる行為を行う必要もある。
そこで、君主には「美徳と悪徳の見せ方」、つまりセルフプロデュース力が大切なのだという。
マキャベリの基本方針は「愛されるよりは恐れられる方が良い。ただ憎悪されてはいけない」だ。
例えば「気前良く与えること」は美徳だが、常に気前良くあろうとすると財力を失ってしまう。
吝嗇は美徳とはいえないが、状況によっては支出を絞る必要もある。
新たに領土を広げたときなど、人民の支持を取り付ける段階では気前良くばら撒き、安定運営の段階になったら支出を切り詰め人民の負担を軽減する、などメリハリが大切になる。
さらに、残虐行為など「君主の地位を危うくするような悪徳」においては、君主が致命的な汚名を被ることがないよう、スケープゴートとしての行為者を用意すべきだとしている。
その後の立憲君主制や戦前の天皇制のように、君主と実際の行政執行者を分けることでイメージコントロールをする。考え方としては普通なのかもしれないが、この時代にそのアイデアを明確に言葉にしたのは先進的だったのだと思う。
まとめ
マキャベリは「実際の物事の真実を追求するのが適切」だとして、徹底的にリアリストの立場から本書を表している。
そのため、一見すると冷たく非道徳的に映るが、じっくり読み込むと「戦乱の続く世で、人民の痛みを最小限にする現実的な方法」を追求していたのだということがわかってくる。
そのエッセンスは現代でも活かせる部分がたくさんある。
今回紹介した5点以外にも、鋭い意見がたくさんあり、とても面白い本だった。
ぜひ、実際に本書を手に取って読んでみることをお勧めします。