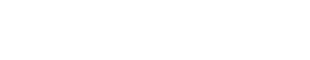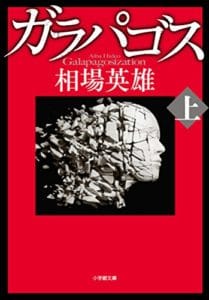震える牛
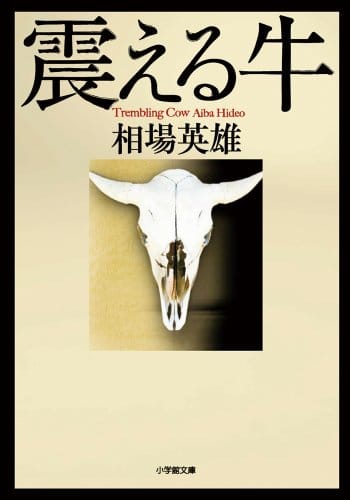
こちらで購入可能
あらすじ
警視庁捜査一課の田川は、2年前に中野の居酒屋で発生した強盗殺人事件の捜査をしていた。
殺されたのは、獣医師の赤間と、裏社会と繋がりのある産廃業者の西野のは二人で、初動捜査では入り込んだ強盗にたまたま殺されたものだと考えられていた。
捜査を進めるうち、二人が殺された状況が不自然であることや、犯人が逃走に超高級車を使っていることから、金目当ての強盗とは思えない状況が明らかになる。田川は「赤間と西野を殺すことが目的の事件だったのではないか」と考え捜査方針を転換した。
田川は、初動捜査を指揮したキャリアの管理官から妨害を受けながらも、直属上司や同僚の支援を受け調べを進めていく。
地道な鑑取りの結果、大手ショッピングセンター「オックスマート」取締役の柏木が捜査線上に浮かび上がってきたが、柏木と被害者との繋がりや動機が見えない。柏木は政治経済界での影響も大きく、不完全な状況で逮捕に踏み切ることはできないでいた。
田川は、オックスマートの闇を追っていたジャーナリストの鶴田と接触し、少しずつ糸口をつかんでいく。
感想・考察
プロローグとエピローグにある通り「行き過ぎた自由主義との戦い」が本書のテーマとし、「自由主義 = 資本主義下での競争主義」がもたらした歪みを描いている。
一つ目が、内臓や皮などを加水分解して混ぜ込んだ「カサ増し肉」の問題だ。
個人的には「食糧生産の工業化」や「食品添加物の使用」自体を否定するつもりはない。
食料生産が工業的手法で安価になったことで飢えから救われた人は、粗悪な食品による健康被害を受けた人よりも多い。保存料の効果で食中毒を逃れた人も、保存料による健康被害を受けた人よりも多いことは間違いない。
地球上で爆発した人口が支えるのに、これらのテクノロジーは不可欠だ。
だが、不幸だったのはこれらのテクノロジーが「行き過ぎた自由主義」と出会ってしまったことだ。
消費者が求めるレベルで釣り合いが取れていれば良いのだが、資本主義下の競争が「必要以上に安く、必要以上に便利に、必要以上にキャッチーに」していく。
他の供給者より少しでも安ければシェアを取れるのであれば「質の良い商品を提供しよう」という倫理観が怪しくなってくるのも理解できる。
そして消費者側も、手元に余裕があっても「本当にこんなに安い必要があるのか」と考えることなく、少しでも安い方に目が向いてしまう。
本書で描かれるもう一つのテーマ、巨大なショッピングセンターが地域の商店街を破壊するのも同じ構造だ。
規模を大きくすることで物流費などのコストを削減することは、消費者にも供給者にとってもメリットだ。流通が整備されていない地方に多種多様な製品をもたらしたことも大きな貢献だと言えるだろう。
だが、ショッピングセンター運営会社が薄利多売の自社ビジネスよりも、テナント料収益にうま味を見出すと「人の流れを作る力」に値段を付ける不動産と同じビジネスモデルになる。
だが、不動産ビジネスと違い「人がそこに住む」というような実体的な必要性がない分、成長力がなくなればいずれ行き詰まる。
それが、地元商店街などのコミュニティーを破壊したあと儲からなくなって撤退し「焼き畑ビジネス」と揶揄される状況を引き起こすのだろう。
ここでも「競争原理」が不幸を引き起こしているのだと思う。
売上を拡大し利益を拡大しなければ生き残っていけない構造が競争を煽り、少しでも高かったり、不便だったりする経営が許容されなくなる。
消費者側も良く考える必要があるだろう。
本当にそれほどの便利さを求めているのか、100円のおにぎりが200円になったら生活が破綻するのか。
「死ぬようなことでなければ、少しくらい損しても気にしない」という鷹揚さが、長期的に見て社会に多様性を残しより大きな利益をもたらすのではないか。
本書がテーマにしたのはショッピングセンターだが、近年ではネット上の企業が更に極端な寡占化を進めている。リスクは拡大していると言える。
「2個買うと、1個無料!」の洗剤を買い物かごに入れながら考えてみた。