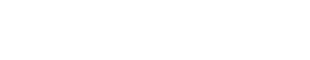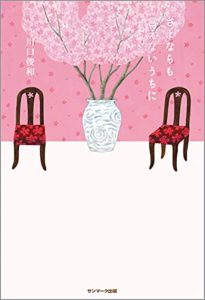ソラリス

こちらで購入可能
あらすじ
2つの太陽を持つ惑星「ソラリス」と、その「海」の振る舞いが長らく研究されてきた。
心理学者のケルヴィンはソラリスの探査ステーションに到着したが、先任の研究員でかつての指導者でもあったギバリャンが自殺したと聞きショックを受ける。
残っていた研究員の一人スナウトは何かを隠している様子で、もう一人の研究員サルトリウスも自室に閉じこもって出てこようとしない。
ステーション内を調べていたケルヴィンは、そこにいるはずのない黒人女性が歩いているのを見たが、彼女はケルヴィンに何の興味も示さず去っていってしまう。
ケルヴィンがステーション内にいるはずのない人を見つけたことを知ると、スナウトも状況を語り始めた。
スナウトもサルトリウスも、そこにいるはずのない自分と深いかかわりのある人である「客」をステーション内に見つけ、精神的に追い詰めれらていた。ギバリャンが自殺したのも、そのせいだったという。
数日後、ケルヴィンが目覚めたときに、かたわらにハリーがいるのを見つける。
ハリーは10年ほど前にケルヴィンと一緒にいたが、彼との諍いが原因で自殺した女性だった。
彼女は10年前の姿そのままで、ケルヴィンのことは覚えていたがそれ以外の記憶があいまいになっているようだった。また少しの間でもケルヴィンと離れることができない様子だった。
その存在を怖れたケルヴィンは、ハリーを脱出用ロケットに閉じ込め射出してしまう。
だがスナウトは「彼女は帰ってくる」という。
惑星ソラリスは2つの太陽を持つため本来なら軌道は不安定になるが、その「海」が影響を及ぼし、軌道を安定させ一定範囲の環境を保っていた。
また「海」は様々な振る舞いを見せ、時に巨大な構造物である「長物」や、何かを模倣した「擬態形成体」などを作り上げることが知られていた。
今回の「客」も「海」が探査ステーションに送り込んだものと考え、ケルヴィンはその意図を知ろうとする。
またケルヴィンは、再び現れたハリーに恐れを感じつつも愛情を抱くようになる。かつてオリジナルのハリーを傷つけたことへの自責の念に襲われていたが、やがて、そこにいるハリー自身が大切な存在となる。
ハリーはギバリャンが残した記録から自分がコピーであることを知り、また自分の存在がケルヴィンを追い詰めていることを知った。
彼女はサルトリウスが開発した「客」を物理的に消滅させる装置を使い、自分を消滅させることを選んだ。
ハリーの喪失に打ちのめされたケルヴィンだったが、彼女の後に残された可能性を感じ、ソラリスに残ることを決意した。
感想・考察
人類と地球外知的生命体とのコンタクトを描く作品だ。
人間は無意識に「人間形態主義」に引きずられ、自分のフィルターを通して物を見ることから逃れることはできない。
そういう制限がありつつも、ソラリスの「海」のイメージは、奔放で自由だと感じる。「2001年宇宙の旅」と同じくらいの衝撃を受けた。
まずその形態が独特だ。「海」に例えられるように巨大な一つの生命体で、構造も動き方も地球上の生物の範疇を逸脱している。
またその「知性」も人間の知性とは大きく異なっている。そのことが、ソラリス研究員たち、そして読者に不気味さを感じさせるのだろう。
ケルヴィンは、ソラリスの「海」が ハリーを送り込んできた「意味」を考えた。友好のつもりなのか、精神的な攻撃なのか、反応を見る実験なのか。
人間にとって「意味」の分からないことは恐ろしい。逆に、どれほど醜悪であっても意味が分かれば安心できるところがある。
だが「目的」から意味を知ろうとする手法は、「海」には通じない。
一つの惑星に一つしか存在せず、死がプログラムされているわけでもない「海」は、生存のために環境に働きかけ周囲を変えていく必要はない。
地球上の生物は進化論的な生存競争を勝ち残ってきたものだとすると、自分の生存という「目的」が常にあり、大部分の行為は「目的」のための「手段」である、というのが共通のフォーマットなのだろう。
「海」のように、競争も死という時間制限もない存在であれば、「目的」を持たずに「刺激に反応するだけ」ということもあるのかもしれない。それでも長い時間を経て「知性」を蓄積することはできるのかもしれない。
だが人間からは理解しがたく、その分からなさが不気味なのだろう。
視点を広げてくれる快感を味わえる、素晴らしいSFだった。