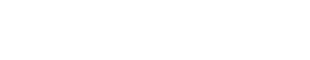ネメシスの使者
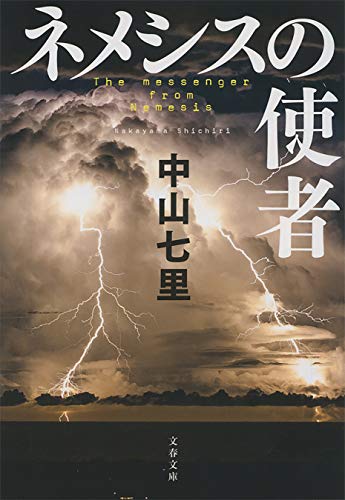
こちらで購入可能
さすがの「どんでん返し三回転」。
1回転目:意外な犯人(よくできたミステリだ)
2回転目:犯人の真の目的(なるほど、そう来たか!)
3回転目:罪と罰と贖罪のちゃぶ台返し(ネメシス、そっちかよ!)
と来ます。
中山七里さん本領発揮の「司法を舞台とした罪と贖罪の物語」を舞台に、裁判官、検察官、刑事、被害者遺族、加害者家族などなど、様々な立場の人を通して死刑制度について語る。
作中の裁判官は「死刑制度廃止派と存置派の議論は胡乱な水掛け論」だという。
犯罪抑止力や冤罪のリスクなどの理屈は、立場によってどうにでも解釈できる。「刑罰は復讐のためにあるのではない」と言いながら、結局は遺族や世間一般の感情に根拠を置いているようにみえる。
例えば米国では、死刑制度を廃止した州の方が存置している州より殺人事件の発生率は低いという事実がある。だがこの事実も解釈次第で色々な見方ができる。
死刑と殺人の直接的な因果関係と解釈すれば「死刑は殺人抑止に繋がらない」ということになるだろう。
逆向きで因果関係を考えれば「殺人事件が多いから死刑制度が必要とされている」といえるかもしれない。
あるいは、共通の原因の影響を受ける相関関係にあるのかもしれない。例えば「その土地の攻撃的な文化・伝統が、多くの殺人を引き起こし、同時に死刑存置が優勢になる状況を生んでいる」というように。
因果関係を恣意的に切り取れるのであれば、功利的な立場で「最適な結果を生むための最適な施策」を決めることに意味は無い。だとすれば、正義に関することは結局、個人もしくはその社会を擬人的にみた「主観」に基準を置くしかないということだ。
例えば日本には今でも死刑制度がある。
功利的な根拠はなく、世界でも死刑廃止が趨勢となっている中、未だ存置されているのは、日本という社会が「主観的・感情的」に死刑を求めているからだといえるだろう。
日本には100年ちょっと前まで「敵討ち」の制度が残っていた。
今の日本人で「忠臣蔵」に入り込める人は少ないと思うが、感情移入できないのは「主君への忠義」が理解できないからで、「大事な人を奪われたら、自分の手で殴り返したい」という感覚は多くの人が持っているのではないだろうか。
表面的なシステムなどは外圧で変わることがあっても、「正義」に関わる部分では、擬人化した日本社会の「主観」が変わらない限り、変化することはない。
ベンサムからロールズに連なる「功利主義」は、経済の問題は解けても、「正義」には踏み込めない。
サンデルのいうように、文化や伝統を共有する「共同体」をベースとした考え方でなければ捉えられないのだろう。
この「ネメシスの使者」では、それぞれの立場の登場人物が死刑を軸に「罪と罰と贖罪」について語る。
終盤までは上述したような流れで展開するけれど、最後の最後でちゃぶ台返しがあり、あえて作者の立場を曖昧にして終わる。「ちゃんと自分の頭で考えろよ」という突き放しで終わるのは、中山七里さんらしい。
深く考えさせられる傑作。
是非、手に取って読んでみてください。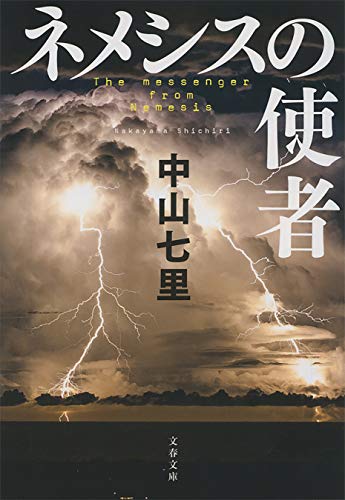
あらすじ
一人の女性が殺された。
捜査をすすめ、被害者は通り魔事件犯人の母親だと判明する。
現場には被害者の血で「ネメシス」というメッセージが残っていた。
被害者が犯罪加害者の家族であり、義憤の女神ネメシスの名が残っていたこともあって、事件はかつての通り魔事件への復讐だとみられる。通り魔の犯人は2人の無抵抗な女性を殺したが、死刑にはならず無期懲役を受けていた。
次いで、ストーカ殺人犯の父親が殺される。
この犯人も2人を殺しながら死刑を免れ懲役刑に服していた。その現場にもネメシスの名が残されていたことから、ユルい判決に義憤を覚えたものの犯行だという見方が強まった。
捜査に当たった警察と検察は、「温情判決」を出した裁判官や弁護士に警護をつける一方、同じようにユルい判決に至った過去の事件をリストアップし犯人を絞り込む。
ちょうどその頃、とある殺人事件加害者の家族から「誰かに狙われている」という通報を受け、警察は罠を張った。